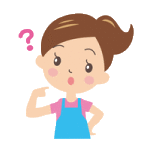公的年金のしくみ2:年金は現役世代から高齢世代に支払われる(賦課方式と積立方式)
記事内に商品プロモーションを含む場合があります
老後資金というと、自分で積み立てたお金を将来受け取るというイメージがありますが、日本の公的年金はそのような仕組みではなく、現役世代が今支払っている保険料は現在年金を受け取っている高齢世代へ支払われる年金となっています。
このような方式を賦課方式といいます。
自分が支払った保険料分の年金がもらえない?
- 現在の日本の公的年金は現役世代が支払った保険料は年金受給世代の年金となる賦課方式により運用されている
現在、日本の公的年金は賦課方式により運営されていますので、現役世代が今支払ったお金が自分の年金となることはありません。
年金の運用方法は大きく分けて2つあり、賦課方式に対して、自分で積み立てたお金を自分の年金とする方式を積立方式があります。
■年金の運用方法
- 賦課方式:現役世代が支払った保険料を現時点の高齢者の支給年金に使用する
- 積立方式;現役世代が支払った保険料を将来の自分の支給年金に使用する
現役世代の人から見ると、最低限自分で支払った保険料分の年金を受け取ることのできる積立方式の方が良いと感じる人が多いかもしれませんが、賦課方式は保険料を支払ってから実際に年金を受け取ることができるまでに物価が大きく上がった場合に実質的な受給額が下がるリスクを避けることができます。
逆に積立方式は大きく物価が上がるインフレリスクには弱いですが、その分自分が支払った分の保険料は年金として受け取ることができ、高齢者と現役世代の比率に左右されないというメリットがあります。
■賦課方式と積立方式のメリット・デメリット
| メリット | デメリット | |
|---|---|---|
| 賦課方式 | インフレリスクに対応することができる | 自分が支払った保険料より少ない年金になる可能性がある現役世代と高齢者のバランスが崩れると破たんする |
| 積立方式 | 自分が支払った保険料分の年金を受け取ることができる | インフレに弱い |
賦課方式、積立方式はそれぞれにメリット・デメリットがあり、現在の公的年金制度では賦課方式が採用されていると理解しましょう。
少子高齢化が賦課方式の日本の公的年金を直撃
賦課方式であるがゆえに、今の現役世代がいくら年金をもらえるかは、あくまで自分が年金を受け取ることのできる年齢になった時の現役世代、年金受給世代の人数などによって異なります。
現在は約2人の現役世代で1人の年金受給者を支えていると言われ、2050年には1.5人の現役世代で年金受給者を支えることになると言われています。
■高齢世代(65歳以上)を何人の現役世代で支えているか
| 年 | 高齢者1人を何人の現役世代で支えているか |
|---|---|
| 1960年 | 11.2人 |
| 1980年 | 7.4人 |
| 2000年 | 3.9人 |
| 2020年 | 2.2人 |
| 2050年 | 1.5人 |
日本は少子高齢化が進んでいるので、確実に現役世代の人数は減り、年金を受給する高齢者が増えています。
そのため、賦課方式ではこのままだと現在の支給水準を保つことはできず、支給水準を下げるか保険料を上げるしかありません。
現在の日本は支給水準を下げる方向で対応していて、「マクロ経済スライド方式」という方式をとって、現役世代の減少や寿命が伸びたことによる高齢世代の増加に対して年金水準を少しずづ下げており、物価が上がっても年金額は変わらないという厳しい状況になっています。
賦課方式を取っている以上、現役世代と高齢者のバランスに依存することになるので、若年世代になるほど年金は厳しくなり、それに伴って自分で準備する老後のお金が多く必要になっているといえます。
自分にあったお金の相談相手を見つける
老後のお金に対する不安を解消するには専門家に相談するのが一番で、特定の金融機関に属さないFPは大切なお金のことを相談する相手にぴったりです。
住んでいる地域や年齢、家族構成から自分にあった相談相手を探すことができるので、簡単に無料相談ができます。
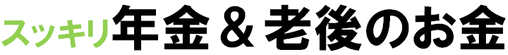
 高齢者1人に対する現役世代の人数と現役世代の負担割合
高齢者1人に対する現役世代の人数と現役世代の負担割合